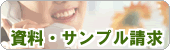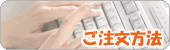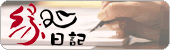「健康寿命」をのばす、という考え方。
健康寿命とは、一生のうちで、介護などを受けずに、
自立して日常の生活を送れる期間のことです。
生きている間は、自分の力で動き、
自分で身のまわりのことができ、
自分で食事をし、自分で思いを伝え、
生活を楽しみたい。
「健康な状態」で「長生き」することこそ、大切に!
◆◆ 健康寿命をのばすということ ◆◆
「人間は血管とともに老いる」
これは、約100年前に、医学者のウイリアム・オスラー博士が言った言葉です。
言い換えれば、「血管を老いさせなければ死なない」ともいえるわけです。
“不老長寿”は、人々に共通する願いなのかもしれませんが、
やはり、人間は年齢とともに老いていくのが、自然の流れなのだと思います。
医療の進歩で、命を“生かしておく”ことはできるようになりました。
しかし、それは、本当に幸せなことなのでしょうか。
「健康な状態」で「長生き」することこそ、大切にすべきだと考えています。
「健康寿命」をのばす、という考え方です。
健康寿命とは、一生のうちで、介護などを受けずに、
自立して日常の生活を送れる期間のことです。
生きている間は、自分の力で動き、自分で身のまわりのことができ、
自分で食事をし、自分で思いを伝え、生活を楽しみたい。
それは、誰もが望むことでしょう。
脳卒中は、後遺症が残る確立が高い病気です。
もしも発症した場合、今の段階では約3割の人に、
介護が必要な後遺症が残るといわれています。
もちろん、実際に発症しても、その後何事もなかったかのように生活できる人や、
軽度の後遺症のみで、それほどの不自由なく暮らしている人も多数います。
相当な覚悟と努力で後遺症と闘い、障害を抱えながらも、
すばらしい人生を送っている人も多くいます。
しかし、やはり脳卒中にはならないでほしい。
「脳卒中にならない生き方」
「脳卒中の危険因子」を、しっかり遠ざけ、あるいは管理すれば、8割は防げます。
ところが、そうはいっても、発症する人を完全になくすことができないのも事実です。
「脳卒中にならない、負けない生き方 より」

イライラしたり、焦ったときは、手首のタッピング。
どうにもやる気が出ないというときは、
薬指の第一関節のところを優しく揉んでマッサージ。
左右どちらの手でも、時間も好きなだけ。
「気持ちいいな、気分がよくなってきたな」
と感じるまででOKです。
イライラしたときは手首のタッピング、やる気を出したいときは薬指を揉む
イライラしたり、焦ったとき、簡単にできる対処法があります。
それは、手首のタッピングです。
腕の表側、手首から指3本分ぐらい上(肘側)のところを、
もう一方の手の指(人差し指と中指)で、
軽くリズミカルにタッピングする。
そうすると、イライラしたり、パニックになっていたものが、
案外と、落ち着いてきます。
なぜなら、手首の少し上には、副交感神経を上げてくれる
ツボがあるからです。
また、どうにもやる気が出ないというときは、
薬指の第一関節のところを優しく揉んでマッサージすること。
そこには、交感神経を上げてくれるツボがあるので、
揉むことで、心の活力も上げてくれるからです。
そして、タッピングも、薬指のマッサージも、
左右どちらの手でもかまいません。
また、時間も好きなだけ。
みなさんが「あ、気持ちいいな、気分がよくなってきたな」
と感じるまででOKです。
「「これ」だけ意識すればきれいになる。 より」

死んでしまった神経細胞は復元しないけれど、ほかの
ルートで代用できれば、言葉がある程度話せるように
なり、失語症もよくなっていくということです。
言語障害はその期間を過ぎても、新たなルートを
開拓できるわけですから、運動麻痺にもその可能性が
ないとは言い切れないと考えられています。
脳科学の発達によって、さまざまなことがわかり、
新たな試みがされています。
可能性のあるかぎり、あきらめずに努力する、
ということが大事なのではないかと思います。
◆◆ 脳にはまだ知られていない「驚くべき力」がある ◆◆
脳卒中は、脳の一部を壊してしまう病気です。
しかし、脳には驚くべき力が眠っています。
運動麻痺は6ヶ月を過ぎると改善が見られなくなるのに対し、言語障害が回復するのは
脳のすごさを物語る、一つの事例です。
たとえば、死んでしまった神経細胞が「言葉を話す」という役割を担っていた場合、
脳からの指令がうまく伝わらなくなるので、しゃべれなくなってしまうのです。
ちょっとイメージしてみましょう。
脳の中では、運動会のリレーのように、神経がバトンをつないで、指令を伝達していきます。
しかし、たとえばC地点の神経細胞が倒れてしまい、指令がそこで止まってしまう、
という事態が起こります。
このとき、すぐにC地点の神経細胞を救出できれば復活したのですが、時間が経ち、
死んでしまって、その指令も届かなくなる。
これが運動麻痺や言語障害の起こる理由です。
ところが、脳のすごいところは、C地点から今度はほかのルートでバトンを渡そうとするのです。
新たなルートで、新たなリレーのチームを作り、「言葉を話す」という指令を伝えようとします。
この新チームは、以前のチームのようにバトンの受け渡しがうまくなく、
スムーズに指令が届きません。
しかし、何度も繰り返し練習するうちに、だんだんうまく指令が伝わるようになっていきます。
このようにして、死んでしまった神経細胞は復元しないけれど、ほかのルートで代用できれば、
言葉がある程度話せるようになり、失語症もよくなっていくというわけです。
運動麻痺に関しては、6ヶ月間、新たなルートを探したり、バトンの練習をしたりしたけれど
ダメだったという場合には、麻痺がそのまま残ってしまいます。
しかし、言語障害はその期間を過ぎても、新たなルートを開拓できるわけですから、
運動麻痺にもその可能性がないとは言い切れないと考えています。
脳科学の発達によって、さまざまなことがわかり、新たな試みがされています。
あきらめずにチャレンジし続ければ、復活の日はいつか訪れるかもしれません。
ものごとに“絶対”はありません。
だから「絶対に治る」こともなければ「絶対に治らない」ということもないのです。
可能性のあるかぎり、あきらめずに努力する、ということが大事なのではないかと思います。
「脳卒中にならない、負けない生き方 より」

 リブラの特徴
リブラの特徴